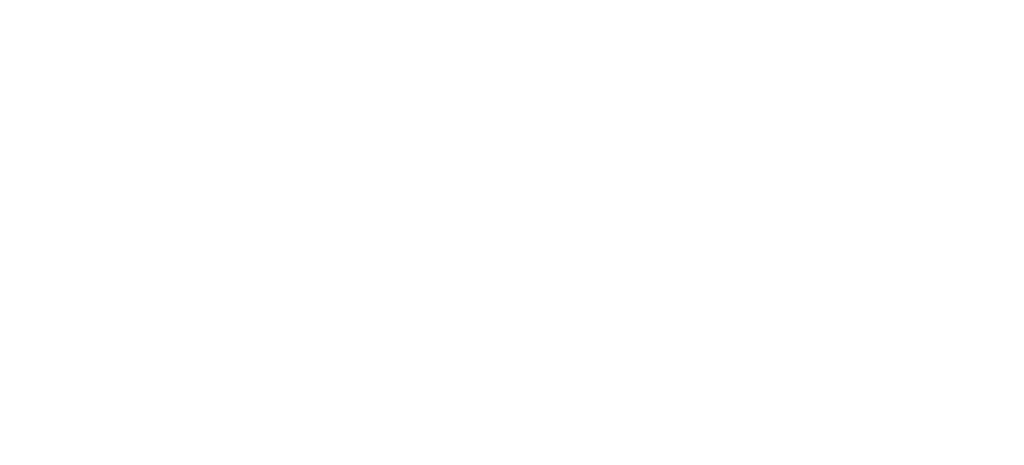模擬講義
開催日時
⑴東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター センター長 瀧靖之先生
10/25(土) 10:30~11:45
「生涯健康脳と認知症予防」
⑵東北大学大学院情報科学研究科 大関真之先生
10/25(土) 13:30~14:45
「東北大学の実学尊重・量子ソリューション創出論」
⑶東北大学大学院文学研究科 鹿又喜隆先生
10/26(日) 10:30~11:45
「世界の土偶、土偶の世界」
⑷東北大学大学院国際文化研究科 妙木忍先生
10/26(日) 13:30~14:45
「観光とジェンダー―北海道定山渓温泉の芸者文化と地域社会―」
場所
川内キャンパス講義棟B棟B204教室
内容
東北大学の教授方による講義をぜひ体験してみませんか?!
⑴ 瀧靖之先生
【講義タイトル】
「生涯健康脳と認知症予防」
【講義概要】
これまで我々の研究チームは生涯健康脳の維持に関わる多くの研究成果を発表してきました。今回の講義ではどのような生活習慣が健康な脳や認知力の維持に有用なのか、また将来の認知症リスクを下げうるのかを述べ、どのような事に気を付けた生活習慣を続けていくのが良いかを、最新の脳科学の知見をもとに講義の中で明らかにしていきます。

瀧靖之先生インタビュー
―現在研究されていることについて教えてください。
瀧先生:簡単にいうと、私たちの脳がどうやって発達をしていくのか、そしてどうやって加齢をしていくのか、何をすると脳を健康に保てるのか、さらには将来の認知症リスクを下げられるのかを研究しています。つまり「脳の発達と加齢、そして認知症予防」が大きなテーマです。
私たちは基本的に脳のMRI、磁気共鳴画像を使っています。多くの方から脳の画像や生活習慣、遺伝子、考えたり判断したりする認知機能に関する情報を集めてデータベースを作り、それをもとに脳の発達・加齢の仕組みや生活習慣の影響を解析しています。結果的に、将来の認知症リスクを下げるための方法を探っているわけです。大規模なデータベースを作り、医学と工学の間のような領域で研究しています。
―脳のMRI画像から、加齢の度合いが分かるのでしょうか。
瀧先生:まさにその通りです。脳の体積は20代後半がピークで、思考・判断・記憶などの高次認知機能も同じ頃にピークを迎えます。その後、脳は加齢とともに徐々に萎縮していきます。ですのでMRIを見れば「だいたい何歳くらいの脳か」というのはおおよそ分かります。
ただし個人差も大きいです。生活習慣が悪い人や動脈硬化のある人、運動不足の人などは萎縮が早い一方で、良い生活習慣を持っている人は脳がしっかり保たれていて、考えたり記憶したりする力も維持されています。
―現在の研究の有用性について教えてください。
瀧先生:一番分かりやすいのは「認知症患者の数をいかに減らすか」という点です。これは個人にとっても国にとっても非常に重要です。認知症による経済的損失は、医療費・介護費・家族による無償介護(インフォーマルケア)を金額に換算すると、年間で約17兆円にのぼるといわれています。
ですから認知症を予防できれば、個人の幸福感や生活の質(QOL)が高まるだけでなく、国民医療費の削減にも直結します。もちろん発症後の治療も大事ですが、突き詰めていくと「いかにならないようにするか」、つまり一次予防に力を入れることが最も重要だと考えています。
―研究の中で一番嬉しかった瞬間、大変だった瞬間はありますか。
瀧先生:嬉しいことも大変なことも山ほどあります。教授になってからは研究よりマネジメントが多いですが、准教授までは研究に没頭していました。その頃一番嬉しかったのは、一晩で2本の論文が受理されたときですね。常に5本、6本投稿していましたから。
逆に大変なことは数え切れません。デザインから論文投稿まで苦労を重ね、ようやく受理されそうだと思ったらリジェクトされることもよくあります。研究はとても大変ですが、それでも楽しくてやめられません。「しんど楽しい」という感じです。
―研究室に欲しい人材について教えてください。
瀧先生:知的好奇心旺盛な人です。出身学部も国籍も性別も問いません。現在、私たちの研究室には56人が在籍していて、医師だけでなく心理学や社会学、文学など多様な背景を持つ人が集まっています。
脳は心理、教育、経済、地域社会などあらゆる分野につながります。医学と工学はもちろん、農学や経済学、文学などとつなげることで新しい研究が生まれます。特定の領域だけで研究しても成熟しすぎて細部に入り込むだけになりがちですが、異分野を橋渡しすると飛躍的に新しい発見があります。文系理系を問わず、脳科学が好きで好奇心旺盛な人に来てほしいですね。
―年内の目標はありますか。
瀧先生:特に「年内の目標」というものは考えたことがありません。常に毎日全力で走り続けています。それが自分のスタイルです。
―学生に伝えたいことはありますか。
瀧先生:好奇心を持ち、好きなことを全力で突き進むこと。これに尽きます。そして英語のリスニングとスピーキングを磨くこと。読み書きは皆さんできますが、話せないと海外では知的能力が大きく制限されます。英語ができれば世界が大きく開けます。
―大学生時代の思い出を教えてください。
瀧先生:私は東北大学理学部生物学科に現役で入りました。祖母が認知症になったことをきっかけに医師を志し、4年生のときに卒業実験をしながら半年間猛勉強し再受験して医学部に入り直しました。大学時代はとにかく友人に恵まれ、理学部でも医学部でもたくさんの仲間ができました。講義も実験も部活もアルバイトも楽しく、充実した毎日でした。東北大学は自由度が高く、やりたいことを突き詰められる素晴らしい大学です。もう一度生まれ変わっても東北大に入りたいですね。
―行きつけのお店はありましたか。
瀧先生:昔「満腹食堂」という店が川内の近くにありまして、毎日のように通っていました。残念ながら今はもう取り壊されてしまいました。
―最近夢中になっていることはありますか。
瀧先生:趣味が多いので、一つに絞るのは難しいですね。ピアノやドラムといった楽器演奏、筋トレ、スキー、読書、車など。芸術や建築を見ること、ファッションも好きです。
「美の追求」というのが自分の中で大きなテーマで、美しいものを見たり聴いたりすると脳の報酬系が働いてワクワクします。美は脳科学とも密接に関わっています。だから音楽やアート、デザイン、文学、ファッション -様々な領域で活動しています。やりたいことはすべてやる。それが私のスタイルです。
⑵大関真之先生
【講義タイトル】
「東北大学の実学尊重・量子ソリューション創出論」
【講義概要】
学んだことは実際の社会に役立たせることはできるだろうか。
そんな不安を感じながら大学に進学し将来を夢想する。
受験生の志望学科選びも少なからず影響するだろう。
君が学んだ二次関数や三角関数は、物理の知識は、ここに役立つ。
実際に取り組んできた企業との共同研究や先輩たちの研究成果の様子を紹介する。
そこで活躍するのは日本発の量子アニーリングである

大関真之先生インタビュー
Q. 今、研究していることについて教えてください。
世の中には、無数の選択肢から最も良い組み合わせを見つけ出す「最適化問題」というものがあります。この問題を解くための新しい計算機として「量子アニーリング」が今注目されています。私はその後押しするための応用研究をしています。これは、自然現象を利用して答えを導き出すのが特徴です。例えば、ボールが高い場所から低い場所へ自然に転がり落ちるように、エネルギーが最も低い安定した状態を自動的に見つけ出す仕組みを利用します。解きたい問題に合わせて、数式などを設定し、あとは自然に答えが導き出されるのを待って、その結果を読み取るだけで、複雑な問題を解くことができます。
Q. 今行っている研究の有用性は何ですか?
この手法は自然現象をベースにしているため、従来のコンピュータのように複雑なアルゴリズムを学ばなくても、直感的に扱うことができます。つまり、様々な人が研究や開発に携わりやすくなる、ということです。このように、開発への「参画の敷居」を大きく下げられる点が、この研究の最も大きな有用性だと考えています。
Q. 研究で一番嬉しかった瞬間、大変だった瞬間は何ですか?
<大変だった瞬間>
ある研究で、指導教員が「結果はきっとこうなるはずだ」という強い予測を持っていました。しかし私は学部4年生の時から「その予測は違うのではないか」と進言していました。そして博士課程1年の終わり頃、その予測が間違いであることを示す決定的な証拠を見つけたのです。 早速、指導教員にそのデータをぶつけたのですが、全く信じてもらえず、説得するのが本当に大変でした。3度目に説明に行った時、ようやく「面白いじゃないか」と認めてもらえましたが、そこに至るまでの時間は大変でした。ただ、この経験を通して、研究者はこれほどまでに厳しく議論を重ねるのだと体感でき、大きな学びになりました。
<嬉しかった瞬間>
大変だったことの続きになりますが、研究の世界では、指導教員と進めた研究は共著で論文にするのが通例です。しかし、その論文が書き上がった時、彼に、最初はあなたの説を否定し、信じなかったから、君一人の名前(単著)で発表しなさいと言われました。これは本当に嬉しかったです。
Q. 自分の研究室には、どのような学生に来てほしいですか?
どんなことでも面白がり、目の前で起きた小さな変化や発見を喜べる人に来てほしいです。研究には辛い瞬間もありますが、どんな些細な進展でも皆で喜びを分かち合えることが大切だと思います。もちろん、知識や数学の能力も大事かもしれませんが、それ以上に、毎日一つでもちょっとでも面白いことがあったら面白いって言える人が欲しいと思います。
Q. 年内の目標は何ですか?
今、YouTubeをやっていて、チャンネル登録者数が11,333人(※インタビュー時点)なのですが、年内に東北大学の学生数を超えるのが目標です。
Q. 学生に伝えたいことはありますか?
私の口癖は「一度やってダメなら2回やれ、2回やってダメなら3回やれ、3回やってダメなら5回やれ」です。今の時代は、インターネットのおかげで、何かを始めるきっかけは簡単に見つかります。もちろん、ネットの情報が常に正しいとは限りません。しかし、とにかく「試す」ことができる素晴らしい時代です。だから、まずは1回やってみてほしい。 1回でうまくいかなくても、それは失敗ではなく、「やり方が悪かっただけ」です。なら、やり方を変えてもう1回やればいい。結局、この試行錯誤の回数が多い人が成功するのだと思います。あとは、「1回凹んでショック受けても、死にやしないから」も口癖です。とにかく挑戦すること。ダメならまたやること。これを伝えたいです。
Q. 大学生時代の思い出を教えてください。
塾講師のアルバイトです。始めた初年度は生徒が全く集まらず、本当に困りました。そこで、話し方を変えたり、授業で使うオリジナルキャラクターを作ったりと、様々な工夫を凝らしました。すると、その努力が実を結び、夏期講習では満員御礼になるほどの人気講師になることができました。あの時の苦労を乗り越えた達成感が、今の自分を支える原体験の一つになっている気がします。
Q. 行きつけのお店はありますか?
「ピッツェリア ろっこ」です。仙台のいろは横丁にあるのですが、僕が思う世界で一番うまいピザです。友人に紹介されて以来、通っています。
Q. 最近、夢中になっていることは何ですか?
台湾ティーです。もともとタピオカは好きではなかったのですが、先日台湾で飲んだものが衝撃的においしくて。そのお店のタピオカは粒がとても大きく、満足感がすごかったんです。この「食べごたえ」がうまさの秘訣かと、夢中になっています。
⑶鹿又喜隆先生
【講義タイトル】
「世界の土偶、土偶の世界」
【講義概要】
縄文時代を象徴するもののひとつが土偶です。その用途については諸説ありますが、明確な根拠を示して説明されることが少ないです。今回の講義では、近現代の北方狩猟民の民族事例にみられる人形から土偶の用途に関する仮説を出し、実際の土偶の分析からその仮説を検証します。また、南米エクアドルの土偶と比較することで、その特徴を明確化します。

鹿又喜隆先生インタビュー
Q. 今、研究していることについて教えてください。
遺跡の年代学と遺物の痕跡学をおこなっています。特に旧石器時代の遺跡を発掘して遺跡に残る炭水化物等の遺跡に残る炭化物等の放射性炭素年代を測定することによって、遺跡がいつのものかを決定します。また、痕跡学は遺跡から出土した石器等の残され方や石器に残る製作や使用の痕跡から、当時遺跡で何が行われたかを明らかにします。これによって、いつ、どこで、何が行われたかという歴史像を描くことができます。
Q. 今行っている研究の有用性は何ですか?
私の専門とする石器の痕跡学のエキスパートは決して多くはありません。そのために、国内外の知り合いから分析依頼を受けることがあります。その結果、様々な国や地域で分析を行い、研究成果を発表することができました。これは研究面だけでなく、自分自身の世界観を広げてくれる点でも有益です。
Q. 研究で一番嬉しかった瞬間、大変だった瞬間は何ですか?
考古学では発掘による大発見があるというイメージがあります。そのため、一番うれしかったことが発掘での大発見と思われがちです。私の場合、いままで分からなかった遺跡の年代や当時の人々の行動の証拠を見つけることができたときがうれしいです。小さな発見を積み重ねて、歴史像を語ることができた時に嬉しさを実感します。
Q. 自分の研究室には、どのような学生に来てほしいですか?
考古学に強い関心と情熱をもった人。できれば、心身ともに健康で考古学の研究を続けて行ける人。
Q. 年内の目標は何ですか?
今年は3ヶ所の発掘が予定されています。そのうち、栃木と山形での発掘は終わりました。これからもう一つの発掘を宮城県内で行います。それを無事に終え、年末の学会で報告することが年内の目標です。
Q. 学生に伝えたいことはありますか?
研究では、地味で時間がかかる基礎研究ほど大事だと思います。一見目覚ましい成果のように見える研究領域にばかり気を取られずに、しっかりと足元の、目の前の課題をクリアしていくことが大事だと思います。
Q. 大学生時代の思い出を教えてください。
長く学生をしていたので、色んな思い出がありますが、研究室の発掘調査時の友人や先輩・後輩との様々な思い出は人生の財産だと思います。
Q. 行きつけのお店はありますか?
店名は明かせませんが、焼き鳥屋とラーメン屋、飲み屋でしょう。
Q. 最近、夢中になっていることは何ですか?
子供と一緒に、映画やジムなどに行く時間を大切にしています。
⑷妙木忍先生
【講義タイトル】
「観光とジェンダー―北海道定山渓温泉の芸者文化と地域社会―」
【講義概要】
この授業では、日本の社会史的背景と地域固有の歴史を振り返りながら、戦後の旅の大衆化、高度成長期に隆盛した芸者文化、その中で生きてきた女性たちに注目します。また、地域の女性たちや男性たちが、芸者さんの子育てに協力して芸者さんのライスコース選択を支えていた実態と、1970年代当時の当該地域社会の仕組みにも触れたいと思います。

妙木忍先生インタビュー
Q. 今、研究していることは何ですか?
今は、芸者文化と地域社会の研究をしています。ほかに、長期間考え続けているテーマもあります(医学博物館と女性の身体表象について2006年から考えていますがまだ結論は出ていません。コンテンツツーリズム研究では徳島県三好市山城町に関心を持っています)。
Q. 今行っている研究の有用性について教えてください。
私は大学院生のときに、東京で指導教員から、「解きたい問いは自分で立てる。立てる問いは、それゆえ、一人ひとり違う。他人の問いを解く必要もなければ、自分の問いを他人に解いてもらう必要もない。」ということを学び、自分の問いを立ててそれを解いていく楽しみを存分に味わいました。当時は、ライフコース選択をめぐる女性間の対立と葛藤の研究をしていました。のちに『女性同士の争いはなぜ起こるのか 主婦論争の誕生と終焉』(青土社、2009年)として刊行されました。いま私たちが生きている時代がどのような時代なのか、なぜ男性や社会にも関わりのある論点が女性だけの論点のように現われてくるのか、その仕組みを知りたいとも思っていました。これは「私の」問いでした。自分に関わる切実な問いでした。このように、私をとらえて離さない問いがありました。当事者性がありました。と同時に、もしかすると、いろいろな世代の女性たちにもこのテーマは共有されるかもしれないと思いました。そのときに「有用性」はあるのかもしれませんが、基本は「私の」問いです。つまり、「有用性」のために研究をしているわけではありません。
また、私は、秘宝館というある特定の時期に隆盛し、ある特定の時期に衰退していった遊興空間の、日本文化における歴史的意味や、その文化を創ってきた方々の人生にも関心を寄せるようになり、他の人のライフヒストリーを聞かせていただくことも多くなりました。つまり、自分自身と結びついている研究も、そうではない研究もおこなってきました。それでも、いつも大切にしているのは、当事者性であり、その方々の人生に触れて、その時代や社会を分析することをしてきました。今は芸者文化(なくなった地域も、残っている地域もあります)に関心があります。ある現象から日本社会や当該時代を分析するとともに、その文化に携わっている方々の人生に思いを寄せています。「有用性」はあるかどうかわかりません。ただ解きたくて解いています。
Q. 研究で一番嬉しかった瞬間、大変だった瞬間は何ですか?
<嬉しかった瞬間>
「嬉しかった瞬間」は、いくつかあります。一つ目は、博士論文執筆中に自分の問いを解いている時間のすべて。二つ目は、元祖国際秘宝館伊勢館が2007年に閉館したときに譲り受けた医学模型23点を、国内の大学医学部に寄託し、永年保存されることになったとき。三つ目は、秘宝館研究を終えて(『秘宝館という文化装置』青弓社、2014年)、その研究が歴史に位置付けられたとき(丸善出版から2019年に刊行された『展示学事典』に「秘宝館と展示」という項目ができてそれを執筆したときや、熱海秘宝館の2024年のリニューアルで「秘宝館の歴史」というブースが新設されて監修をしたときなど)。また、秘宝館研究で秘宝館を作った人々のライフヒストリーを聞かせていただいて、その情熱や思いや軌跡を知り、お人柄に触れさせていただいたことも幸せな時間でした。
<大変だった瞬間>
ある「大変だった瞬間」は、次のとおりです。私は、迫真性の高い複製身体や医学模型の研究もしているので、蝋人形館や医学博物館に入ることがあります。2006年にロンドンのマダム・タッソー蝋人形館に入ったときに、お化け屋敷のようなコーナーがあり、動くかもしれないし動かないかもしれない蝋人形のところ(つまり蝋人形と本物の人間が混じっている場所)を通らなければならなかったとき、研究とはいえ、とてもこわかったです。マダム・タッソー蝋人形館の原稿はのちに、「観光化する複製身体―マダム・タッソー蝋人形館をめぐって」というタイトルで『フェティシズム研究 第3巻 侵犯する身体』(京都大学学術出版会、2017年)に書きましたが、その背景にどんなこわい体験があったのかは、もちろん書いていません(笑)。原稿には表れない、いろいろな体験をしながら研究をしています。
Q. 自分の研究室には、どのような学生に来てほしいですか?
「これを解きたい」という自分自身の問いを持っていて、それを解こうとしている学生さんに来てほしいです。
Q. 年内の目標は何ですか?
年内の目標というよりは、いつも心がけていることを続けていくことになるのですが、健康に気をつけて、一日一日を大切に、そして確実に過ごしていくことです。
Q. 学生に伝えたいことはありますか?
私たちのまわりには、問いがたくさんあります。そして、その中から「自分の解きたい問い」を見つけ、それを自分で解いていく過程そのものを一人ひとりに楽しんでほしいと伝えたいです。
Q. 大学生時代の思い出を教えてください。
私は教育学部にいたのですが、さまざまな科目の授業に出て楽しかったです。調理実習の授業では、「妙木さんは何でもできそうで、何にもできないんですね」と先生から言われました(笑)。農学部の授業に出て牛のお世話をしたり、体育の授業では柔道をしたり、他大学の学生と合同でおこなわれる合宿形式の授業に参加したり、授業関連の思い出がたくさんあります。
Q. 行きつけのお店はありますか?
行きつけすぎて内緒です。
Q. 最近、夢中になっていることは何ですか?
自分の専門分野とは全く別の本を読むことです。新たな分野について学ぶことが、すごく楽しいです。
趣味は旅行です。知らないところに出かけることが好きです。